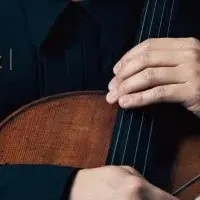

昭和名曲の誕生秘話と両親への想いを巡る感動特集
昭和名曲の誕生秘話と両親への想いを巡る感動特集
2023年5月14日、水曜の夜8時より放送される「そのとき、歌は流れた」では、昭和の名曲を生んだ偉大なアーティストたちが特集されます。今回は、小柳ルミ子さんと川中美幸さんが出演し、それぞれの名曲の誕生秘話や、歌に込めた思いを語ります。
小柳ルミ子と『瀬戸の花嫁』の誕生秘話
小柳ルミ子さんは、彼女のデビュー曲として知られる『瀬戸の花嫁』のどうやって生まれたのか、その背景について語ります。通常、曲と歌詞はどちらか先に生まれ、そこに歌手が命を吹き込むのが一般的ですが、今回の楽曲は異なるアプローチが取られました。作詞家の山上路夫さん、作曲家の平尾昌晃さんが別々に作り上げた曲と歌詞が一緒になった瞬間、小柳さんはその美しさに強く心を打たれたといいます。「背中に電流が走った」という言葉が、彼女の感動を物語っています。
川中美幸のドラマティックな音楽体験
一方、川中美幸さんは、自身の名曲『ふたり酒』について語ります。この曲には、彼女自身が感じた両親への強い想いが込められています。川中さんにとって、この楽曲はあくまで自分の「等身大の曲」心持ちではなく、両親の人生の一端を映し出したものです。彼女が24歳のとき、自身がつらい現実を生きていく中で、「お前と酒があればいい」という男口調の歌詞に少し戸惑いを感じたものの、実際に母親がその曲に感動して涙し、その瞬間にこの歌が売れると確信したと語ってくれました。
名曲に秘められた思い
川中美幸さんが語る興味深いエピソードとして、歌の登場人物の感情を通じて自分の気持ちを整理し直す様子があります。前述の『遣らずの雨』は彼女が聴いた時に鳥肌が立つほどの衝撃を受けた楽曲であり、さらに周囲の反応も意外なものであったことを赤裸々に明かしました。関係者からの「それは川中美幸の世界ではない」という言葉も響きましたが、彼女はその歌を通じて独自の視点を持つことができたといえます。
番組の特徴と他の名曲
この番組は単なる名曲紹介に留まらず、昭和の世相を元に、歌の歌詞が人々にどう響いたのかを深く掘り下げていきます。レコードが一般的ではなかった当時、商店街やラジオ、テレビから名曲が流れ、誰もが口ずさむ時代でした。皆が共通して抱いていた感情を歌に乗せたことで、名曲は強い支持を受け続けてきたのです。
さらに、番組内では母の日にちなんだ特集も披露され、田川寿美さんの『おかあさん』や青山新さんの『円山・花町・母の町』、そして山口百恵さんの『秋桜』といった、母と子にまつわる名曲が流れます。これにより、視聴者は昭和の名曲を介して多くの思い出を思い返すことができるでしょう。
最後に
昭和の名曲は時代を超えて、多くの人々に愛され続けてきました。「そのとき、歌は流れた」の放送を通じて、皆さまに希望と感動を与えるこの特集をぜひお楽しみください。





トピックス(音楽)
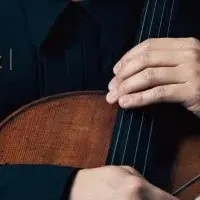
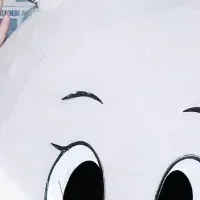


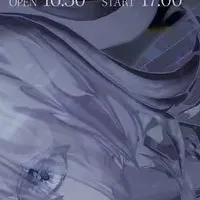

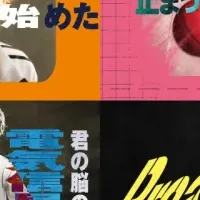

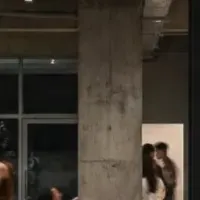
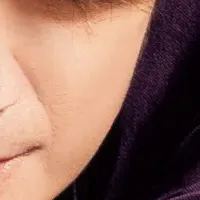
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。