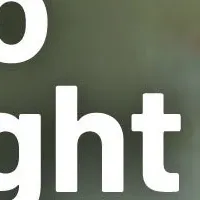

冨永愛が挑戦!高知の伝統「フラフ」制作の魅力とは
冨永愛が体験する「フラフ」制作の舞台裏
毎週水曜日の夜10時に放送されている「冨永愛の伝統to未来」では、モデルであり文化支援者の冨永愛が日本各地の伝統文化を紹介しています。2月5日の放送では、彼女が高知県香美市にある吉川染物店を訪れ、フラフの制作に挑戦しました。フラフとは、江戸時代から伝わる伝統的な工芸品で、端午の節句に子供の健やかな成長を願って鯉のぼりと共に揚げられる特製の旗です。
フラフの歴史と魅力
フラフの起源は諸説ありますが、江戸時代にオランダ商人によって持ち込まれたとされています。その後、高知県独自の文化として発展を遂げ、形や色彩が多様化してきました。特に高知の人々は「目立つこと」に重きを置き、大きなサイズのフラフを作り続けているのも特徴的です。吉川染物店の店内には、畳17畳分という巨大な旗が飾られており、その迫力に富永愛も圧倒された様子でした。
手作りのこだわり
フラフの制作は全て手作業で行われ、絵柄の決定から色染めに至るまで一つ一つの工程に丁寧さが求められます。五代目の吉川毅さんから話を聞くと、節句に揚げるにあたって「武者」や「金太郎」などのモチーフが人気だそうです。最近では、クジラに乗った金太郎など、ユニークなリクエストも増えているとか。特に、吉川さんは裏面も色を染めるという徹底したこだわりを持ち、その技術がより良い仕上がりにつながっていると語りました。
冨永愛の初体験
今回の放送では、冨永愛が初めてフラフ作りに挑戦します。彼女は波を描いたデザインに色を塗るという作業を体験し、吉川さんからのアドバイスを受けつつ、作品制作に没頭しました。その姿は緊張感が伝わってきましたが、作業を通じて職人の技術や情熱に触れる貴重な体験となりました。
完成したフラフは、吉川さんの手によって約1ヶ月かけて仕上げられ、視聴者へのプレゼント企画が用意されています。そして、番組内では「北陸の伝統を未来へ紡ぐ」コーナーも放送され、能登半島地震で被災した珠洲焼作家・有賀純一さんの活躍も特集されました。彼は岡山県備前市の焼き物工房で新たな作品作りを継続しており、珠洲市の共同窯が復活したことで自らの作品を焼く機会も増えています。
番組の見どころ
「冨永愛の伝統to未来」は、伝統文化が抱える問題や、未来に向けた希望を探る内容となっています。高知の伝統工芸「フラフ」を通じて、視聴者に国の文化の大切さを再確認させるエピソードとなることでしょう。次回放送は2月5日(水)よる10時から放送されるので、お見逃しなく。
公式サイトで詳細をチェック!
番組公式SNSでは、冨永愛のオフショットやオフタイムの様子も配信中です。ぜひ、チェックしてみてください!


トピックス(その他)
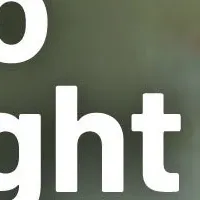


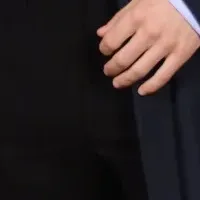
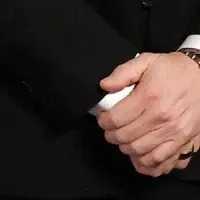

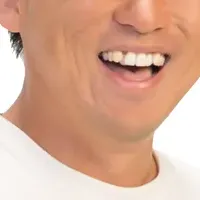



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。