

音楽療法を科学で探求する!『音楽療法は科学になり得るか』の魅力
音楽療法の新たな視点が開かれる
音楽療法士や教育関係者にとって、専門知識は常に求められています。そんな中、長年の経験を有する龍野弘毅氏が著した『音楽療法は科学になり得るか』が、アマゾン限定で発売されました。この書籍は、音楽療法士が知っておくべき基本知識から脳科学、心理学、発達論までを網羅し、音楽療法の可能性について体系的に解説しています。
音楽の力を科学で理解する
音楽は歴史的に見ても、人類にとって重要なコミュニケーションの手段であり、感情を豊かにする存在です。しかし、その科学的根拠やメカニズムに迫ることはあまり行われてきませんでした。本書では、音楽が脳や感情に及ぼす影響について、最新の研究を基に解説されています。特に、共感やコミュニケーションとの関連や、自閉症、認知症のケアとしての可能性にも触れています。
社会を一つにする音楽
音楽が持つ集団をまとめる力についても考察されています。労働歌、校歌、国歌といった音楽は、文化や時代を超えて人々の心を一つにし、社会的な結びつきを強める役割を果たしています。それはただの感覚ではなく、脳の機能に基づくものです。音楽を聴き、歌うことで分泌されるドーパミンが快感や一体感を生むメカニズムについても詳しく説明されています。
音楽療法士に必要なスキル
音楽療法を行うには、ただ楽器を演奏したり歌ったりするだけでは足りません。本書では、「刺激」と「鎮静」といった音楽の効果をどのように活用し、クライアントとの共感を深めるか、さらには即興音楽の取り入れ方について実践的に掘り下げています。これにより、音楽療法士が必要とするスキルや知識が具現化されています。
誰におすすめか
『音楽療法は科学になり得るか』は、以下のような方々に特におすすめです:
- - 音楽療法士や音楽教育に携わる方
- - 音楽と脳・心理学の関係に興味を持つ方
- - 発達障がいや認知症などへの音楽の利用を考える方
著者からのメッセージ
龍野氏は、著者として「音楽療法には医学的エビデンスだけでなく、心理学や社会学の視点も不可欠」と語ります。彼が提案するこの書籍が、音楽療法を実践する方々に新たな視点を提供し、多くの人に音楽の力を体感してもらえることを願っています。
龍野弘樹のプロフィール
1971年に大阪音楽大学を卒業し、多岐にわたり音楽活動を行ってきた。1985年からヤマハ音楽振興会での業務を開始し、1998年から音楽療法の研究を本格的に始める。2001年には「音楽応用研究所―MIND」を設立し、音楽療法の実践を続けている。
書籍情報
『音楽療法は科学になり得るか』は356ページにわたり、音楽療法の多様な側面を探る一冊です。販売価格は1,980円(税込)で、アマゾンにて手に入れることができます。興味のある方はぜひお手に取って、その魅力を体感してください。
この書籍は、音楽療法の可能性とその科学的基盤を理解する上で、非常に貴重なリソースとなることでしょう。
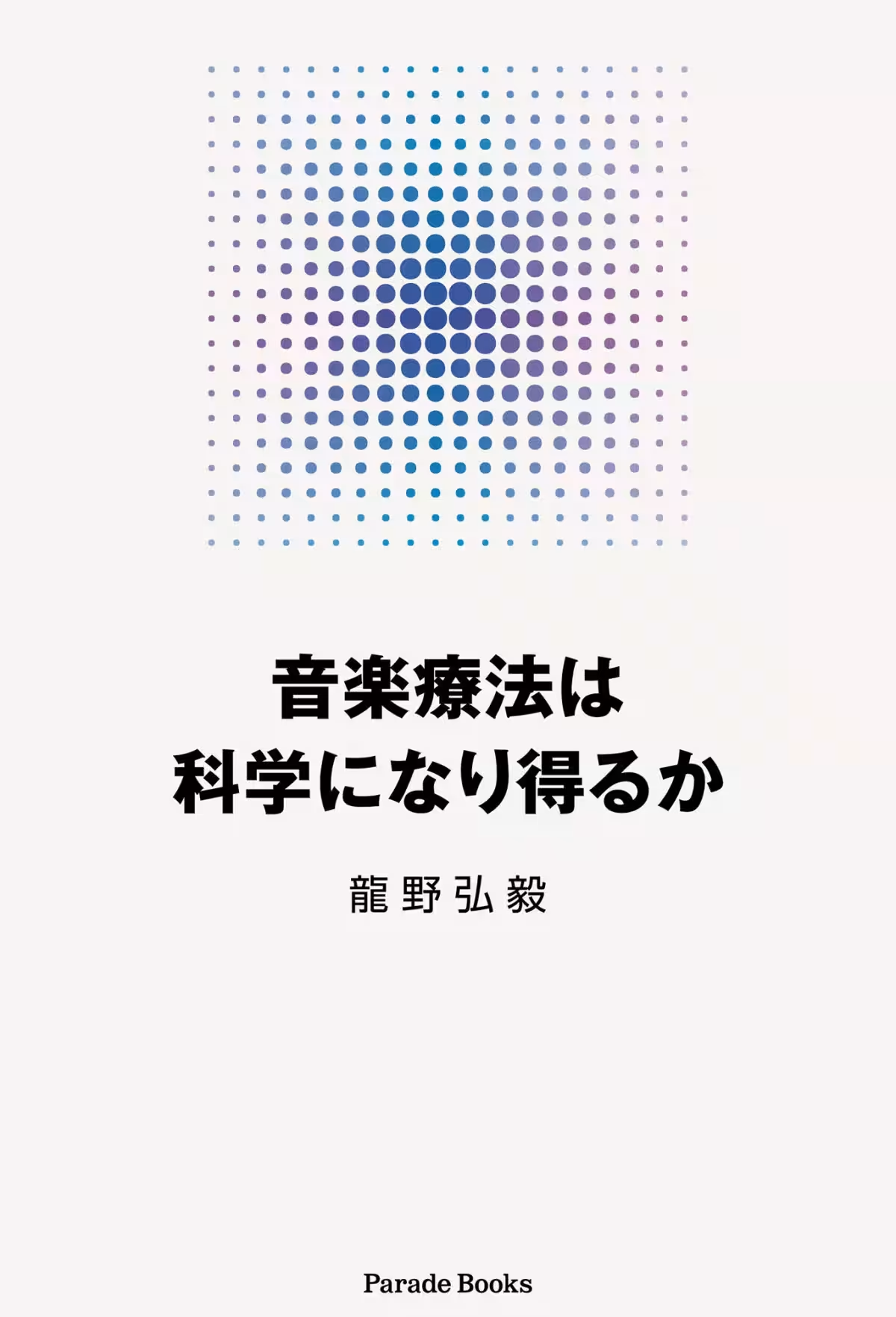

トピックス(音楽)








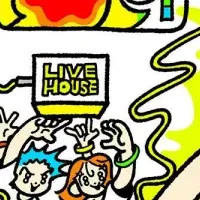

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。